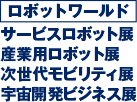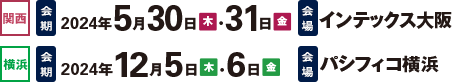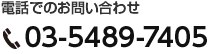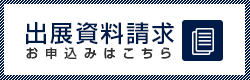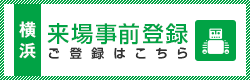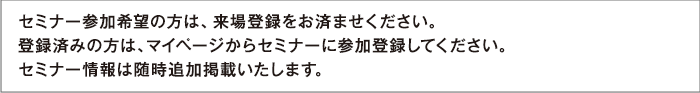
10月23日(木) 10:30-11:30
10月24日(金) 12:00-13:00
宇宙探査からのAI・ロボティクス技術への期待

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙探査イノベーションハブ
山崎 雅起 氏
2010年4月-2015年9月 株式会社東芝, 研究開発センター
2015年10月-2021年9月 株式会社本田技術研究所,ロボティクス部門
2021年10月-現在 JAXA,宇宙探査イノベーションハブ
[セミナー内容]
JAXA宇宙探査イノベーションハブは、将来の月探査および火星へ発展可能な自動・自律運転型の次世代モビリティシステムの構築を目指しています。モビリティに関するサービス提供は、月面活動の初期的段階では南極付近での調査や資源利用のため、少量、近距離での資材移動・運搬が主たる目的となりますが、将来的には月面拠点の構築や月の広範囲にわたる物資と人の移動へと発展拡大することが想定されています。
そこで、宇宙探査イノベーションハブで行ってきた月探査におけるAI・ロボティクス技術の研究例を紹介し、今後募集する次世代モビリティシステム構築のためのAI・ロボティクス技術について述べる。
10月23日(木) 10:30-11:30
ソフトロボティクスの社会実装に向けたアカデミアの取り組み

北陸先端科学技術大学院大学 HoAnhVan研究室 博士後期課程 2年
只野 利恩 氏
2024年~北陸先端科学技術大学院大学 博士後期課程在籍中。大学時は、AI開発やweb製作、アプリケーションの開発など多岐に渡り活動を行う。柔らかい素材を使ったソフトロボットに出会い、大学院から転専攻。現在は、博士研究と平行しながら、大学発ベンチャー起業を目指し活動している。
[セミナー内容]
近年、人手不足などの課題を解決するため、様々なロボットが社会導入されています。特に、ソフトロボットは、柔らかさを活かした柔軟な動きにより、食品・製造・医療分野を中心に世界的に注目されています。しかし、ロボットビジネスには様々な課題があります。一方、大学では、研究成果の社会実装に向け、スタートアップが推進されています。本講演では、ソフトロボットの研究成果と、そのビジネス化に向けたスタートアップの活動についてご説明します。
10月23日(木) 12:00-12:30
ロボット産業成長に貢献する TECH HUB YOKOHAMA

横浜市経済局 イノベーション推進課 担当係長
長崎 一男 氏
大学卒業後、日本興業銀行にてデリバティブ取引、リスク管理、国際業務企画などに従事。その後、米系IT企業の日本法人代表、コンサルティング会社のディレクター、ヘルスケア系スタートアップの経営陣として事業開発を推進してきた。2024年6月より横浜市経済局にて、これまでの知見を活かしエコシステム形成に貢献している。座右の銘は「生涯現役」
1980年3月東京大学経済学部卒業
2006年3月東京大学工学系大学院 MOTコース受講
[セミナー内容]
横浜市はTECH HUB YOKOHAMAを昨年11月に開設し、テック系スタートアップにフォーカスした成長支援を実施しています。ロボット産業はディープテックの中でも重要な領域であり、横浜の社会課題解決力とものづくり技術を基盤に、「横浜版ロボット・エコシステム」の構築を検討しています。今後は、国内外の大学・研究機関・企業R&D・投資家との産学官金連携によるエコシステム強化を更に図り、実証実験フィールドの提供を通じ、ロボットフレンドリーな未来を横浜から創造します。
10月23日(木) 13:30-14:30
ソフトウェアで支える宇宙開発 ~これまでの歩みと未来への挑戦~

株式会社セック 執行役員
松久 孝志 氏
数十にわたる宇宙関連プロジェクトに参画。小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」、月面で話題となった変形型ロボット「SORA-Q」など、数々のミッションの成功に貢献してきました。
現在は「ソフトウェア技術で宇宙開発の課題を解決する」をコンセプトに「Space HAX Project」を推進し、火星移住時代を見据えた次世代宇宙技術の研究開発に取り組んでいます。
[セミナー内容]
当社は創業以来、リアルタイム技術とシステムズエンジニアリングを駆使し、50年以上にわたり日本の宇宙分野に貢献してまいりました。本セミナーでは、その歩みを振り返るとともに、次世代構想「Space HAX Project」をご紹介します。「自律進化」をキーワードに、宇宙システム自体が学習・適応・進化する革新的なアプローチにより、宇宙開発の課題解決に挑んでいます。本講演では、宇宙産業における新たなパラダイムシフトと、自律進化するソフトウェア技術が切り拓く未来の可能性をお伝えします。
10月23日(木) 13:30-14:30
RobiZyが描く、宇宙サービスロボットの世界

株式会社2moon 代表取締役社長
NPO法人ロボットビジネス支援機構(RobiZy)宇宙部会長
愛媛大学 防災情報研究センター 特定准教授
伊巻 和弥 氏
30年以上の宇宙開発業務の中で、スペースシャトル、国際宇宙ステーション(ISS)、深宇宙探査、衛星データ利用等幅広い業務を経験。主にこれから宇宙産業参入を目指す企業を支援し、日本の宇宙産業拡大に向け底辺を支える。
専門はSpace Robotics。ISS「きぼう」のロボットアームを始め、日本が開発した8種類のロボットシステムの開発・運用に携わる。ここ2年間で約30社の企業コンサルを実施。
[セミナー内容]
今や宇宙は生活の一部となり、空との境界線はなくなりつつあります。宇宙旅行が始まり、宇宙に年間1,000人が暮らす世界は夢ではなくなりました。宇宙は特別なものではないのです。宇宙政策を見ると2030年代初頭に宇宙産業を8兆円規模へ増大させ、新たに宇宙産業への参入を目指す企業を「宇宙戦略基金」等で強く支援しています。
今回のセミナーでは、RobiZy宇宙部会が現在特に力を入れている、ISSや月面経済圏におけるサービスロボットプロジェクトの検討状況と宇宙用サービスロボット標準について説明します。当部会活動にはどなたも参画可能です。セミナー内容にて興味を持たれた企業様は、是非一緒に宇宙を目指しましょう。
10月23日(木) 15:00-16:00
BodySharingによる体験共有の未来 ― ロボティクスと感覚伝達の融合

H2L株式会社 代表取締役社長
玉城 絵美 氏
人間とコンピュータの間で身体感覚を伝達するBodyShairng技術の研究と事業開発に従事.2011年,東京大学大学院で博士号取得,総長賞受賞.2012年にH2L, inc.を創業.2020年より5Gと連携した遠隔での体験共有システムを多数提案.
[セミナー内容]
BodySharingとは、身体に付随する感覚を相互に共有し、体験を共有する技術、インタフェースと概念です。私たちはBodySharingを実現するために、光学式筋変位センサを用いてユーザーの力の入れ具合や動きなどの固有感覚を推定しPCに入力する技術や、機械や電気刺激を用いて固有感覚をPCからユーザーに出力するインタフェースについて、研究開発をしてきました。BodySharingはスポーツや医療、遠隔教育、さらにはロボティクスの分野にも応用されています。
本講演では、感覚を扱うインターフェースが、ロボットと生成AIとの関係性をどのように変えるのか、その展望をお伝えします。
10月24日(金) 10:30-11:30
アイデアから社会実装へ:大学研究室から始まる未来づくり

東京理科大学 創域理工学部機械航空宇宙工学科・教授
竹村 裕 氏
2003年9月奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了。2003年10月同大学院 非常勤講師。2004年ドイツ・カールスルーエ大学客員講師。2005年4月東京理科大学理工学部機械工学科助手。その後、助教、講師、准教授を経て、2019年4月同大学(現創域理工学部機械航空宇宙工学科)教授。主として,ロボティクス,生体機械学,生体医工学の研究に従事。博士(工学)。株式会社 Beyond Optical Technologies 取締役。
[セミナー内容]
東京理科大学竹村研究室では、学生と共に多くの共同研究者やスポンサーの支援を受けながら、社会課題の解決を目指したロボット技術の研究開発を行っています。本セミナーでは、研究室で生まれたユニークかつ実用的な技術を紹介します。たとえば、近赤外光を用いた分光画像により、生体組織の識別精度を高めた腹腔鏡は、手術支援ロボットへの応用が期待されます。また、体育館床のささくれ傷を自動で検出・診断する移動ロボットは、人手による検査を効率化し、安全性向上に貢献します。さらに、多様な形状の対象物を柔軟に把持できる装置は、シンプルながら高機能な把持を実現します。研究室から実世界への挑戦を、ぜひ会場でご体感ください。
10月24日(金) 10:30-11:30
ジェロンテクノロジーで切り拓くサービスロボット新産業

東京大学大学院 工学系研究科人工物工学研究センター・特任研究員
本田 幸夫 氏
1980年デンソー入社、1989年パナソニック入社。高効率モータの開発に従事。マレーシア松下モータ経営責任者、モータ社CTO、ロボット事業推進センター長を経て2013年より大阪工業大学教授、ロボティクス&デザイン工学部を創設。2020年より東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター特任研究員、大阪大学大学院医学系研究科招聘教授、日本医療研究開発機構PO兼任、元厚生労働省介護ロボット担当参与。
[セミナー内容]
サービスロボットは、自動車、電気、農業、サービス業など幅広い分野で期待されていますが、長寿高齢社会では高齢者支援に特化したジェロンテクノロジーの活用が重要です。老化を自然な人生の変化と捉え、フレイルや認知症などの課題に対応する技術を実装したAI・ロボット技術が、高齢者の日常生活を支え、「人生100年時代」のwell-beingを実現する新産業を創出します。本講演では、高齢社会に期待されるジェロンテクノロジーの具体的な機能と出口戦略について説明します。
10月24日(金) 12:00-13:00
ロボット技術を基にした医工連携プロジェクト
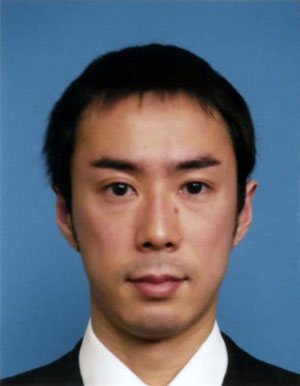
日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)
日本大学理工学部 精密機械工学科・教授
齊藤 健 氏
2001年日本大学理工学部電子工学科卒業。2004年同大大学院修士課程修了。2007年同大大学院博士後期課程満期取得退学。2007年同大文理学部物理・物理生命システム科学科助手。2010年同大博士(工学)。2010年同大理工学部精密機械工学科助手。2016年カリフォルニア大学バークレー校客員研究員。現在,同大教授。ハードウェアニューラルネットワーク,マイクロロボットおよび微細加工技術に関する研究に従事。
[セミナー内容]
日本大学の総合大学としてのメリットを生かし,医学部や芸術学部,理工学部などの複数学部の研究者が参画している,医工連携プロジェクトの研究成果について説明をします。特に,展示もしている腹腔鏡下手術のための「協働型手術助手ロボット」と内視鏡手術のための「腸管内マイクロロボット」について詳しく紹介します。また,腸管内外からの情報を統合した,内視鏡手術と腹腔鏡下手術を組み合わせた手術支援ロボットシステムについても説明します。微細加工技術や集積回路技術を応用したマイクロロボットやニューロロボットについても併せて説明しますので,セミナーを通じて我々の持つシーズを生かして頂けるアイデアを頂ければ幸いです。
10月24日(金) 13:30-14:30
省力化対策としてのロボット活用とは

(特非)ロボットビジネス支援機構・RobiZy
プロジェクトプロモーションオフィサー
村上 出 氏
自動車搭載電子機器の企画・設計・開発、商品開発責任者を歴任後、2009年に早期退職。以降地域産業の活性化・企業の事業支援に伴走型で取組んでいる。
2017年頃から神奈川県内小規模企業へのロボット導入・活用支援に取組み、(特非)ロボットビジネス支援機構の現職として、全国の様々な現場でのロボット活用を支援中。2021年頃から、国や自治体のロボット開発・導入支援専門家としても活動中。
[セミナー内容]
労働生産人口の減少に伴い、企業の大小や地域の違いなく人手不足の時代に突入しています。各社では従業員を確保出来なくなることから、これまでの業務の仕方・プロセスでは、事業継続も危ぶまれています。
今後、業界を問わず、現場では省力化対策の一つとして自動化やロボット活用など、これまでとは異なる生産方式への移行は避けられなくなっています。しかし、多くの企業では、何をどの様に取組めば、効果が得られるかは自社だけでは困難なテーマです。
RobiZyでは生産現場に限らずサービス業の現場も含め、課題解決で結果を残して参りました。本セミナーでは、課題を持つ企業の指針として、参考となるポイントを解説致します。
10月24日(金) 13:30-14:30
ロボットとAIを繋ぐリアルハプティクス
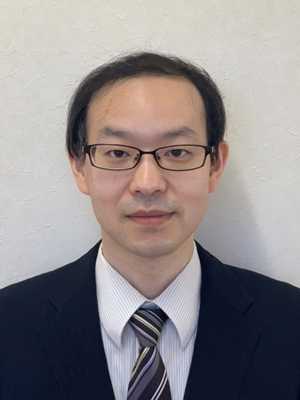
慶應義塾大学ハプティクス研究センター 特任准教授
斉藤佑貴 氏
2011年 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業。2013年 慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年より横河電機株式会社に勤務。2018年 慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。同年より慶應義塾大学ハプティクス研究センター特任助教。現在、同大特任准教授。主として、力触覚伝送制御技術(リアルハプティクス)および機械学習の研究に従事。
[セミナー内容]
なぜロボットは人間が容易にこなせる単純な接触作業の自動化を達成できないのでしょうか?その答えの一つは、ロボットが力触覚を正確にデータ化できないことにあります。何かを見たいなら視覚が必要であり、同様に何かを触りたいなら触覚が必要となります。現在のAI技術開発は、人間の動作における軌道等を基にロボットの自動化を目指すというアプローチが主となっていますが、力触覚情報の欠如が人間のような臨機応変な動作の自動化の難易度を上げています。本セミナーでは、ロボットが力触覚情報を扱うことを可能としたリアルハプティクス技術について、その基本から応用事例、AIとの連携事例について紹介いたします。
10月24日(金) 15:00-16:00
ロボットが生み出すコミュニケーション
~人に寄り添うロボット「RoBoHoN(ロボホン)」と暮らす理由~
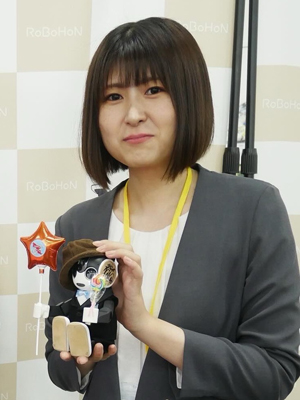
シャープ株式会社
通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部 モバイルビジネス推進部
森 伊吹 氏
幼少期にロボットを組み立てた経験からロボホンに興味を持ち、2021年にシャープに入社。入社直後はスマートフォン開発部署に配属になるも、2023年にロボホンチームへ異動となり、現在はロボホンに囲まれながら、ロボホンの企画業務を担当している。
[セミナー内容]
2016年5月にシャープ株式会社から誕生したロボホン。9年目を迎え、日本全国でどんどんロボホンを愛してくださるオーナーが増えています。人手不足や業務の効率化によって心の通った接客が難しくなる今日、ロボホンのような人に寄り添うロボットがどのような価値を提供できるのか。このセミナーでは、オーナー様からの実際のお声を通して、機能だけではないロボホンの魅力と導入事例についてお話します。
10月24日(金) 15:00-16:00
宇宙建設に係る国土交通省の取組について
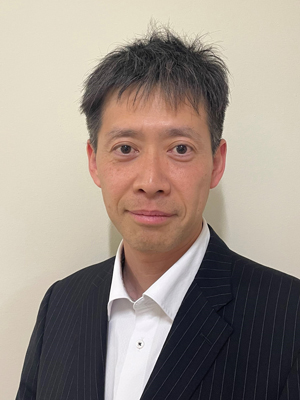
国土交通省 大臣官房 技術調査課
参事官(イノベーション)グループ 施工自動化企画官
菊田 一行 氏
2006年4月 国土交通省 入省
2019年4月 大臣官房技術調査課 課長補佐
2021年4月 総合政策局公共事業企画調整課 企画専門官
2023年4月 近畿地方整備局 猪名川河川事務所長
2025年4月から現職
[セミナー内容]
宇宙利用探査において世界に先駆けて月面拠点建設を進めるためには、遠隔あるいは自動の建設技術(無人化施工等)は重要な要素です。国土交通省では、激甚化する災害対応、人口減少下における生産性向上に対するため、自動施工・遠隔施工等を推進しています。本セミナーではこれらの建設技術の月面拠点建設へ適用するための技術開発と地上の事業へ波及させる取り組みを説明します。
10月23日(木) 10:30-11:30
オープンイノベーション時代の“売れる”商品開発
~横断的共創が生む新しいヒットの法則~

株式会社EnjinPlus
近野 潤 氏
セブン・イレブンージャパン、 ヤオコーで流通業23年従事。2022年株式会社EnjinPlusを設立。商品開発事業を通じて、日本をもっと“ワクワク”する国に!地域や社会に新たな価値や可能性を生み出すための商品開発講座・講演を実施している。著書に「うまいを上手く伝えて売れるを作る驚きの商品開発術」(ダイヤモンド社)がある。
[セミナー内容]
“売れる商品”は一人では作れない。部門や立場を越えた「横断的共創」が、今の時代のヒットを生み出す鍵。現場発の仮説と磨き上げで、お客様の“本当の喜び”を形にする共創型商品開発の実践法を伝えます。
10月23日(木) 11:45-12:15
事例で紹介!大企業発カーブアウトの「超」リアル

BIRD INITIATIVE株式会社 CSO
高木 政志 氏
NECで事業開発部門の設計や複数事業の収益化・売却を経て、BIRD INITIATIVEにてCarve out Studio®を創設。大企業発スタートアップ創出を支援し、2年で3社のカーブアウトと資金調達・自走化を実現。
[セミナー内容]
大企業発スタートアップ創出が国家戦略として加速する中、「カーブアウト」は注目の選択肢となりつつあります。本セミナーでは、なぜ今カーブアウトなのかという最新トレンドや、適したプロジェクトの特徴、親会社にとっての意義まで、現場の知見を交えて解説。実際に3社のカーブアウトを支援した事例をもとに、現実的な課題と可能性を立体的にお伝えします。
10月23日(木) 12:30-13:00
実績に学ぶ 日本企業のイノベーション文化醸成と加速

Ideascaleジャパン株式会社社
エグゼクティブ・アドバイザリー・メンバー
松本 毅 氏
松本氏は、技術戦略立案、オープンイノベーション、国家プロジェクトの推進など、多岐にわたる分野でリーダーシップを発揮してきた、日本のイノベーション分野における第一人者です。現在は 一般社団法人 Japan Innovation Network 常務理事 を務めるほか、NineSigma Japan、リンカーズ株式会社、大阪ガス株式会社にて数々の重要ポジションを歴任されています。
[セミナー内容]
多くの日本企業が直面する「イノベーション文化をどう根付かせるか」という課題。本セミナーでは、国内外の実績をもとに、体系的なアプローチと適切なツール活用により、組織がどのように短期間で成果を上げられるかをご紹介します。AIを活用したアイデア収集・評価・自動化による効率化、全社員が参加できるボトムアップ型の取り組み、さらに社内外を結ぶイノベーション・エコシステムの構築方法を解説。実践的な事例を通じて、貴社の変革を加速させる具体的なヒントをお届けします。
10月23日(木) 13:15-13:45
特化型AIによる実現性の高い開発アプローチ

株式会社モノリシックデザイン 代表取締役
宥免 達憲 氏
NEC系ソフトウェア開発企業、新規事業開発コンサルティング会社を経て、2008年に九州大学発ベンチャーを起業し、データ分析を中心とするシステム提案・開発に従事。その後、2018年にスタジオアリスグループに加わり、AIによる画像補正等の開発を手がけ、2021年3月に現在の株式会社モノリシックデザインを設立。
[セミナー内容]
弊社は約10年以上に渡り、ディプラーニング等AI技術を用いた開発を行っており、お客様の業務に寄り添いつつ、解決すべき問題に対する適切なアルゴリズム選定、学習、チューニングなどをご提案からシステム化まで行っており、実際の現場において長期間稼働している事例が多数ございます。
クラウド等で提供されている既存のAIサービスを利用するのではなく、お客様のデータ、業務フローに特化した独自のAIシステムを作り上げ、高い投資対効果を生み出すことを心がけております。
プレゼンテーションにおいては、弊社のAIに関連した各種事例、ならびに開発のアプローチをご紹介させていただきますので、ぜひご参加ください。
10月23日(木) 14:00-14:30
大学発スタートアップ連携で成果を出すには?
ーオープンイノベーション推進の成功戦略ー

Cross Research LLP 代表パートナー
林 正也 氏
プラスチック業界での研究開発・企画営業などを経て、スタートアップ企業にて新規事業開発コンサルサービスの立ち上げに参画。大手事業会社でオープンイノベーション中心の新規事業開発を経験した後、Cross Researchの代表パートナーに就任。新規事業コンサル、リサーチの全体設計を中心に担当。

株式会社ジー・サーチ データサービス部
中辻 裕 氏
2016年に株式会社富士通総研に入社、2021年に同公共政策研究センター上級研究員を兼務、2022年3月より現職。主に、府省や公的研究機関、民間企業からの受託調査を中心に、科学技術イノベーション政策に関する調査研究や新規研究テーマ策定支援、技術動向調査に従事。
[セミナー内容]
ディープテックや研究シーズの宝庫である大学発スタートアップ。しかし「出会えない」「成果につながらない」と感じたことはありませんか?
本講演では、出資・共創のリアルな成功事例を交えて、成果に結びつく連携の極意を解説します。文化や目的の違い、マッチングのズレといった“見えにくい障壁”の乗り越え方もお伝えします。単なる連携に終わらせず、イノベーションを現実に変えるための実践知をお届け。
さらに、185万人の研究者情報から最適な研究パートナーを探索するためのサービス等をご案内します。産学連携・共創に関心のある大企業・中堅企業の方必聴の内容です!
10月23日(木) 14:45-15:15
イノベーションに欠かせない企業間連携の在り方

ソニーグループ株式会社
Business Acceleration and Collaboration部門
Open Innovation and Collaboration部
Community and Communications Team
統括課長
沼田 洋平 氏
ヤフー株式会社を経て、2016年にソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)に入社。Sony Acceleration Platformでは事業展開のシナリオ構築から販路開拓までを手掛けた「MESHプロジェクト」をはじめ、豊富な事業開発の経験を有する。
[セミナー内容]
本講演では、新規事業・事業開発で多くの企業が直面する代表的かつ本質的な課題や、企業間連携の事例を通じて、オープンイノベーションの実践知を共有します。加えて、境界を越えて新しい価値を創造する、バウンダリースパニングの必要性について紹介します。
10月23日(木) 15:30-16:00
オープンイノベーションの共通言語「体験設計」とその実践

ホロンズ株式会社 代表取締役
髙橋 克実 氏
ホロンズ㈱代表。40年以上にわたり、幅広い産業分野で製品・システム・サービスの設計・デザイン開発を支援。2022年に著書『体験設計~ビジョンから優れた経験価値の創出へ』(丸善出版)を刊行し、その実践活動を推進している。企業間のオープンイノベーションを促進する協業ブランド “Corpex” を立ち上げ、現在も精力的に活動中。
(一社)体験設計支援コンソーシアム代表、日本デザイン学会評議委員、日本人間工学会元部会長、(公財)かながわデザイン機構監事。
[セミナー内容]
DXやAIの進展により、産業界はいま大きな転換期を迎えています。しかし、新素材や新技術といった“手段”だけでは、オープンイノベーションは十分に進展しません。必要なのは、社会の将来ビジョンを見据えた“目的”を持つ「経験価値」のイノベーションです。私たちは、その鍵となる共通言語「体験設計」によるオープンイノベーションを推進するため、体験設計コンソーシアムを設立しました。また、あらゆる産業における新事業・新商品・新サービス開発を、国際的な枠組みで具体的に支援する協業ブランド “Corpex” 事業も展開しています。本セミナーでは、これらの「体験設計」を軸としたイノベーション活動をご紹介いたします。
10月24日(金) 10:30-11:30
オープンイノベーションはなぜうまくいかないか
~その提案書、こうしましょう~
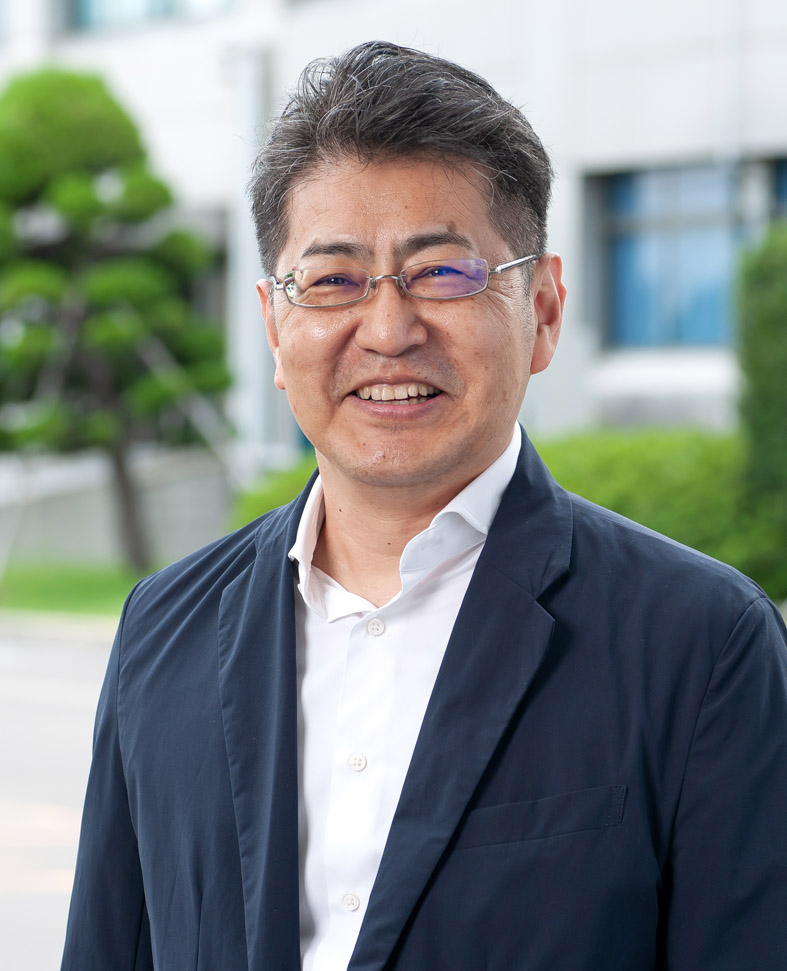
北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携客員教授
樋口 裕思 氏
大阪ガスでオープンイノベーション室長を6年間務め、ニーズ公開型・シーズ公開型・新規事業創出型の3軸を確立。外部スタートアップや大学との連携を加速し、自前主義の5倍超の成果を達成。業界初の定量評価を導入し、社内外から高評価を獲得。
[セミナー内容]
オープンイノベーションを始めたが、なかなか面談や共創に結びつかない…。多くの提案を送っても成果が見えない…。その原因、もしかすると“努力の方向性”かもしれません。本セミナーでは、相手が「ぜひ会いたい!」と思うキラーコンテンツの作り方を、事例とともに徹底解説します。採用や共創につながる提案のコツを学び、提案力を飛躍的に高めます。この機会に、御社のオープンイノベーション活動を加速させましょう!提案が響くと、未来が動きます。
10月24日(金) 11:45-12:45
オープンイノベーション関連政策とNEDOのスタートアップ支援

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
スタートアップ支援部 人材支援・オープンイノベーション促進チーム
チーム長
馬場 大輔 氏
大学における研究職、産学連携部署の専任教員として従事した後、NEDOへの出向を機に転籍。経済産業省にて産学連携、スタートアップ支援等に係る施策・事業立案等に従事した後、2023年より現職。

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
スタートアップ支援部 専門調査員
石嶋 光 氏
大手電機メーカーで、新規事業の企画開発を実施。2020年より現職
[セミナー内容]
NEDO及び経済産業省が支援するオープンイノベーション関連施策について、主にスタートアップとの連携等を中心に、最新の動向等を交えてご説明します。
10月24日(金) 13:00-13:30
「なぜ多くの技術やアセットは、社会実装につながらないのか?」
技術の成熟度合いによって異なる 進め方と投資判断を具体解剖

株式会社ユニッジ Co-CEO
土井 雄介 氏
東京工業大学大学院卒業後、トヨタ自動車に入社。物流改善業務、役員付き特命担当等に従事。並行して、社内新規事業の事業化案に2年連続で選出。その後、AlphaDriveの創業期に出向し数多くの社内新規事業創出に携わる。帰任後、トヨタ社内から事業創出の”しくみ”を構築すると共に、UNIDGEを共同創業。協業による価値創出を推進。累計80社以上の企業支援に関わり、年間60本以上の講演、審査員としても活動。
[セミナー内容]
研究開発や技術資産を活かした新事業づくりは各所で進んでいますが、多くのアセットが“社会実装/事業化の壁”を越えられない現実があります。本講演では、「アセット・技術の社会実装」をテーマとして解説。大手自動車メーカーにて研究開発・事業開発両方の部門を経験した登壇者が、実経験に基づいて体系化させたナレッジをお話しします。
・なぜ多くの技術やアセットは社会実装につながらないのか
・技術成熟度・市場成熟度に応じて異なる、PJTの進め方
・ビジネス(Biz)と研究開発(Dev)をつなぐ組織設計のポイント
・上記の中でオープンイノベーションを活用するには
10月24日(金) 13:45-14:15
新規事業をAIの力で10倍加速する「BIIM Cloud for Business」の
活用方法のご紹介

BIRD INITIATIVE株式会社 マネージャー
中島 美鈴 氏
九州大学大学院にて工学修士取得。武蔵エンジニアリングをはじめ、ニコンや技術系スタートアップにて技術営業・マーケティング・PMに従事し、実務と並行してBond大学MBAを取得。現在はBIRD INITIATIVEにて「BIIM Cloud」の事業化を推進中。
[セミナー内容]
新規事業開発の現場では、情報が散在し、検討プロセスの複雑さが前進を妨げることが少なくありません。「BIIM Cloud for Business」は、AIの力で膨大な試行錯誤、情報を構造化・可視化することで、実行に向けた意思決定を後押しします。本セミナーでは、従来の10分の1のスピードで構想から計画策定へ進める仕組みや具体的な活用シーンを解説。新規事業を推進する新しいアプローチをぜひ体感ください。
10月24日(金) 14:30-15:00
~新規事業の取り組みを徹底分解~
元SBI損保代表五十嵐氏と当時の新規事業の取り組みを振り返る

オフィスエム 共同代表
五十嵐 正明 氏
東京都出身、立教大学卒。外資・国内の生保・損保を経て、2008年 ブロードマインド少短を創業。2011年 少短協会専務理事に就任。2016年 SBIグループに参画、SBI日本少短代表取締役に就任。2019年 SBI損保代表取締役に就任。2024年に独立し「オフィスエム」を創業。現在は複数社の顧問、アドバイザー、パートナーなども務める。著書に「保険業界のゲームチェンジャー ミニ保険を作った7人の侍たち」

seeink株式会社 代表取締役CEO
日比野 由空 氏
20歳〜22歳にかけて、スタートアップ企業から大手企業の新規事業立案に参画。その知見を活かし2020年21歳でseeink株式会社を創業。創業後は中堅、大手企業を中心に新規事業/事業創出を支援。今年で27歳となるが、新規事業の相談を受けてきた案件は2,000件を超える。
[セミナー内容]
元SBI損保代表の五十嵐氏が在任4年間で売上を370億円から520億円へと飛躍的に成長させた要因について、五十嵐氏ご本人と、27歳で2,000以上の新規事の相談を受けてきたseeink代表の日比野で対談を行います。このセミナーでは大企業の経営者の視点から、どのような戦略を描き、いかに組織を動かし150億円もの成長を遂げたのか、企業をグロースさせる新規事業の取り組みについて徹底的に振り返り、実践的なヒントを学ぶことができます。大手企業の経営者の方、新規事業の担当の方は必見です。
10月24日(金) 15:15-16:15
オープンイノベーションにおける3つの成功ポイント

株式会社eiicon Innovation conductor事業部
新宮領 宏太 氏
鹿児島県南九州市出身。新卒で株式会社パソナ入社。株式会社DYMへ転職し、新卒紹介事業の立ち上げを経験。担当企業へ1,000名以上の支援実績を残し、所属部署が2年連続オリコンランキング1位を獲得。子会社の代表取締役も務める。その後、株式会社レトリバに入社。半年後には執行役員就任。4つの新規事業創出に携わり、その中の2つがオープンイノベーションによって事業化。株式会社eiiconへ入社後はInnovation conductor事業部の部長を務める。
[セミナー内容]
主に下記の項目に沿って進めてまいります。
・新規事業が求められる背景
・課題や弱みがむしろオープンイノベーションの好材料に
・オープンイノベーションにおける3つの成功ポイント
・これらを実現していくには